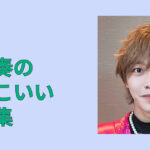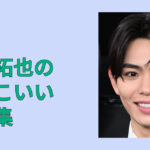|
専業主婦のリアル “肩身の狭さ”と“生きづらさ”とは?当事者「稼ぎに繋がらない。収入がないことがダメな人みたいな…ご飯食べてて申し訳ない」 家事などの主婦業や育児に専念する「専業主婦」。それに対し、「働かないでいいからラクでいいよね」「お金を稼がず生産性がない」「これだけ女性が社会進出… (出典:ABEMA TIMES) |
1. 専業主婦の位置付けと評価

専業主婦という役割は、現代において多様な意見と共に存在し、その評価は大きく変化しています。近年、よく耳にするのは「働かないでいいから楽でいいよね」や「お金を稼がず、生産性がない」という意見です。このような意見は、しばしば専業主婦の重要な役割を見落としていると言わせるでしょう。
専業主婦として家庭を支えることは、家事や育児という目に見える形でない貢献を通じて家庭の基盤を築く、非常に価値のある役割です。しかし、この役割が必ずしも広く承認されているわけではありません。多くの専業主婦が、育児や家事の達成感や意義を感じつつも、社会的承認の不足に悩まされています。
例えば、35歳のあすかさんは、仕事と家事の両立に限界を感じて専業主婦を選択しました。しかし彼女は、「収入がないことが悪いことのように感じる」との思いを抱えています。専業主婦としての選択が、必ずしも自発的なものでない場合も多いのです。やむを得ず専業主婦を選ぶことになったみえさんのように、「選択肢がないことが一番苦しい」と語る人々も少なくありません。
社会全体もまた、これまで専業主婦を支えてきた構造の変化を反映しています。1980年には1114万世帯が専業主婦を持っていましたが、2024年にはその数が508万世帯にまで減少すると予測されています。この変化には、女性の高学歴化や雇用機会均等法の進展、そして経済的な条件が含まれています。
奈良女子大学の岡田玖美子氏もまた、専業主婦が当たり前の社会は過去のものだと指摘しています。女性の社会進出が進む中で、家庭内での役割分担や評価が見直されるべきという視点も重要です。家事や育児に専念する価値が再評価されると共に、専業主婦が孤立することなく、自らの役割に誇りを持てる社会が求められています。
2. 専業主婦の選択とその背景

例えば、あすかさんのように仕事と家事を両立することの難しさを感じ、最終的に専業主婦として家事や育児に専念する道を選ぶケースがあります。彼女は、収入がないことに対する不安を抱えつつも、家庭を支えることの意義を見出しています。
一方で、みえさんのように、自らの意思とは関係なく専業主婦の道を選ばなければならない状況もあります。
彼女にとって最も辛いのは、選択肢がないことです。
これらの例は、専業主婦を選択せざるを得ない背景として、社会的な側面や経済的な圧力が影響していることを示しています。
日本の社会構造や価値観の変化は、専業主婦を取り巻く状況に大きな影響を与えています。
過去には多くの家庭が専業主婦を当たり前のように選んでいましたが、現在は共働きが一般的になってきました。
この変化は、女性の高学歴化や雇用機会均等法の進展、また経済的事情からも影響を受けています。
しかしながら、専業主婦として生きることが選べる社会は、多様な生き方を許容する基盤として重要です。
家事や育児に専念する専業主婦の役割は、家庭の中で重要な位置を占めており、その価値が十分に認識されるべきです。
また、専業主婦としての生き方が肯定される社会では、選ばなくても良かったはずの道を歩むことになった人々の苦しみを減らすことができるかもしれません。
最終的には、専業主婦としての貢献を含めた全ての生き方が尊重される社会が求められます。
家庭や職場のいずれにおいても、女性がより多くの選択肢を持ち、それぞれの選択が尊重される社会を目指したいものです。
3. 専業主婦の割合減少の要因

この変化の背景には、女性の社会進出の進展が大きく影響を与えていると言えるでしょう。特に1980年代以降、女性の高学歴化が進み、それに伴って雇用機会均等法が施行され、女性が職場で活躍できる環境が整備されてきました。
このような社会の変化が、専業主婦から共働き世帯への移行を促しているのです。
また、バブル経済の崩壊後、日本経済は停滞期に入り、多くの家計が共働きを必要とするようになりました。
生活費を賄うためには、家庭内での収入源を増やすことが求められるようになり、それが結果として専業主婦世帯の減少に拍車をかけています。
この他にも、家族の価値観の多様化が専業主婦の存在割合に影響を与えています。
家事や育児を家族全員で分担する意識が高まる中で、夫婦がともに働き、協力し合うスタイルが徐々に一般的になってきています。
こうした変化は、専業主婦に対する社会の見方をも変えてきました。
かつては専業主婦が当たり前とされていた社会が、今では選択肢の一つとして見直されるようになり、働くことを希望する女性たちにとっての選択の幅が広がりました。
しかし、選択肢が増えることで迷いや不安を感じる女性も少なくありません。
社会全体としては、専業主婦であっても共働きであっても、いずれの立場の人々も尊重される環境が求められています。
4. 社会構造と専業主婦の生きづらさ

奈良女子大学の岡田玖美子氏は、専業主婦の孤立感の深刻さを指摘しています。専業主婦が直面する孤立感は、単に個人の問題ではなく、社会的評価の欠如や役割の限定性に起因しています。この状況は、女性が社会進出しやすくなった現代社会において、家事育児の負担が軽視され、社会的に適切な評価を受けられないことにもつながっています。
専業主婦の生きづらさは社会構造の中に根差していると言えます。現代では、女性が高学歴を持ち、雇用の場で活躍することが期待されています。しかしその一方で、家庭内での家事や育児、家族ケアといった仕事はやはり重要であるにも関わらず、社会的承認を得にくいという不均衡があります。この不均衡が、専業主婦に大きなプレッシャーを与え、孤立感を強める要因となっています。
さらに、社会全体として専業主婦を支持しないという風潮も、彼女たちの生きづらさを助長しています。家事や育児を中心とする生活は、経済的生産性がないと見なされがちですが、これらの役割が家族や子供の成長に果たす重要な役割を無視することはできません。家事育児の価値を見直し、家族のために貢献する女性たちが正当に評価され、孤立感を感じずに社会とつながることができる仕組みが必要です。
岡田氏は、専業主婦としての役割とその意義を再評価し、多様な選択肢を持ちつつ、どのようなライフスタイルであっても尊重される社会の必要性を説いています。社会全体でこのような意識を持ち、家族が協力することで、専業主婦として幸せに生きる選択を後押しする環境の整備が求められます。
5. 未来の望ましい社会の姿

現代社会において、専業主婦というライフスタイルはその意義が大きく問われる時代を迎えています。専業主婦の役割には、多くの誤解や偏見が付きまとうことが多いです。「家で働かないなんて、ラクそうだね」や「お金を生まない、非生産的な存在だ」という否定的な意見がネット上で飛び交うこともあります。しかし、家事や育児を通じて家庭を支える専業主婦の役割を再評価することも必要ではないでしょうか。
専業主婦から働く道を選ぶことも必要です。35歳のあすかさんは仕事と家事の両立に悩み、専業主婦となる決断をしましたが、「収入がないことが悪いことのように感じる」との心境を語っています。一方、選択肢がないまま専業主婦となったみえさんは、選択の自由がないことについて、「最もつらい」と話しています。このように、専業主婦の生活には様々な背景や事情が潜んでいます。
少子高齢化が進み、多くの家庭で共働きをせざるを得ない状況が拡大しています。1980年には専業主婦世帯が1114万世帯あったのに対し、2024年には約半数の508万世帯に減少しています。背景には、女性の高学歴化、雇用の平等化、そして経済の変動による影響が挙げられます。奈良女子大学の岡田玖美子氏は、「専業主婦が当たり前」の時代に潜む問題として、家庭内のケアワークが誰によって担われるかという課題を挙げています。特に専業主婦は、「役割が狭い」「評価されづらい」という孤独感を抱えることが多くあります。
みえさんとあすかさんが望むのは、すべての人が自らの選択に幸福を見出すことができる社会です。特に家族の協力が不可欠であり、どちらを選んでも幸福が実感できる社会構造を目指すことが求められています。外での仕事も、家庭内のケアワークも双方が大切です。そのためには、専業主婦としての貢献を正当に評価し、すべての道を尊重する社会を見据えていくことが重要です。
最終的には、すべての人が幸福を追求し続けられる社会の実現こそが望ましい未来の姿であり、この目標に向けて社会全体で取り組む必要があります。