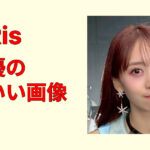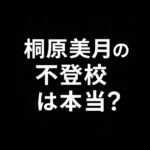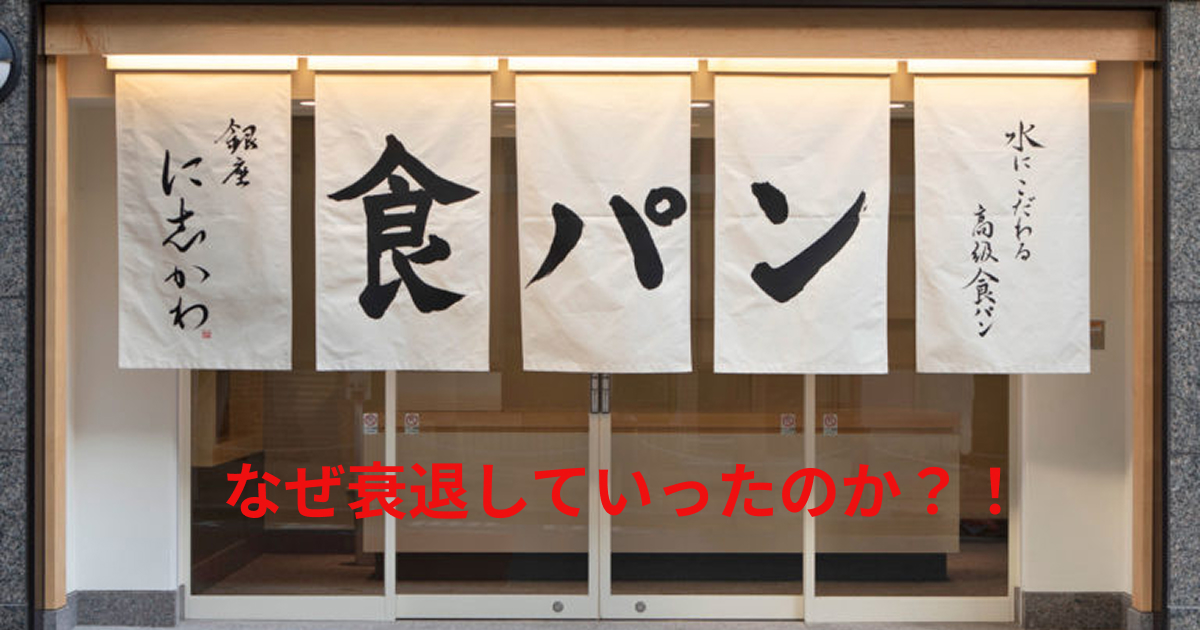
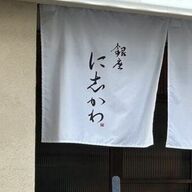 |
大量閉店“銀座に志かわ”はナゼ140→50店舗に減ったのか?「1000円」でも売れた≪高級食パン専門店≫凋落の必然を社長が激白 …かつて2010年代後半に、“高級食パンブーム”が巻き起こったのを覚えているだろうか。 食パンが「1本2斤で1000円弱」ーー。暮らしのプチ贅沢や、手… (出典:東洋経済オンライン) |
1. 高級食パンブームの起源:銀座に志かわ誕生
|
772万円、2025年1月期は14億8,693万円と減少傾向にある。 「銀座 に志かわ 水にこだわる高級食パン」は2019年9月27日に、「銀座に志かわ」は2019年12月20日に、それぞれ商標登録された。店名は社長の高橋仁志の名から「に志」水の川から「かわ」としているが、同業他社が先に登録した商標「い志かわ」と一文字違いである。 [脚注の使い方]…
5キロバイト (379 語) - 2025年7月26日 (土) 06:33
|
一方で、高級食パンブームを一層盛り上げたのは、確実にメディアの影響力です。テレビや雑誌で取り上げられることにより、「食パン戦国時代」や「高級食パンブーム」といったキーワードが消費者に届き、多くのブランドが参入を決めました。この現象はまさに社会現象とも呼べるほどで、ピーク時には全国で1000を超える専門店が次々とオープンし、市場は活気づきました。
しかし、華やかだったブームもやがて終息を迎えます。『銀座に志かわ』など、一時代を築いた店舗数もピークから大幅に減少し、競争の激化や運営コストの上昇、そして消費者の飽きを招き、撤退を余儀なくされた店も少なくありませんでした。また、贅沢志向からシフトし始めた市場の流れも逆風となりました。結局、高級食パンという一点突破型の業態は、持続的な成長には限界がありました。
このようにして、突如として訪れた高級食パンブームも過ぎ去り、多くの店舗は経営の難しさを経験しました。とはいえ、この経験から私たちが学べることも少なくありません。特に飲食業界において、メディアの力やトレンドの動向をいかにキャッチし、対応するべきかといった新たな洞察を得る手がかりとなるでしょう。
2. メディアがもたらした影響

当時、多くのテレビ番組や雑誌が「高級食パン」の魅力を取り上げ、その特集は視聴者の関心を強く引きました。
これにより、消費者の購買欲を掻き立て、店舗に足を運ぶ動機付けとなったのです。
「食パン戦国時代」とも形容されるように、メディアはこぞって特集を組み、特に『乃が美』や『銀座に志かわ』が頻繁に取り上げられました。
これらのブランドは質の高い商品を提供すると同時に、メディアの波に乗り、その存在感を確実に消費者の心に刻み付けたのです。
さらに、メディアが食パンの新たな価値を提示することで、消費者はその贅沢さやユニークさに引き寄せられ、高級食パンは多くの人々の注目の的となりました。
ただ、こうしたメディアの影響の下で多くの店舗が乱立した結果、次第に市場が飽和状態に達し、消費者の興味が薄れてしまう事態にも陥りました。
メディアの力は強大であるものの、それが時に一時的なブームを生み出し、同時にその終息を早める要因となることもあるのです。
3. ブームの衰退原因
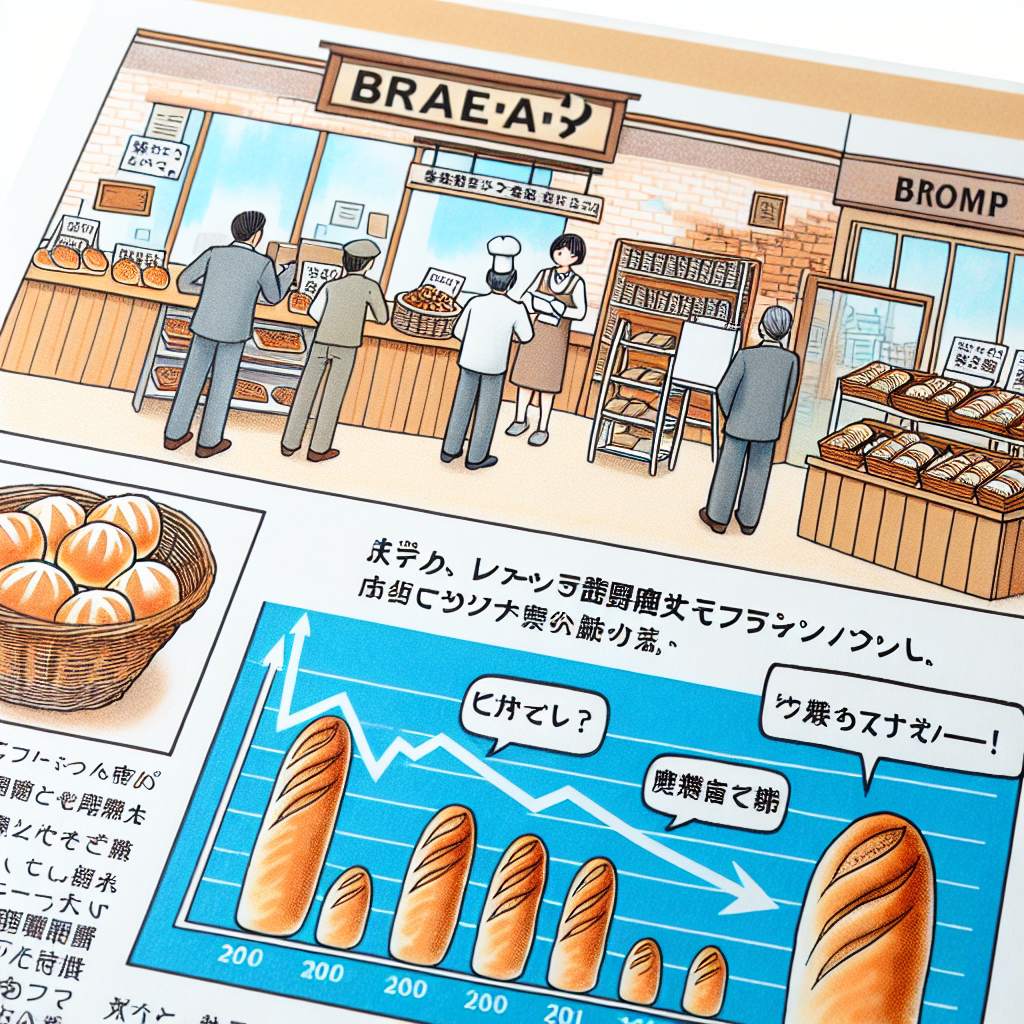
次に、商品価値の持続性に問題があったことも大きな要因です。高級食パンは、生地にこだわり抜いており、トーストせずに楽しめる特徴がありましたが、その価値は消費者に長く伝わりにくく、飽きが訪れるのが早かったようです。一時的な熱狂に留まり、定番商品としての確固たる地位を築けなかったことは、業態的なリスクを露呈しました。
さらに、原材料費や人件費の高騰もブームの衰退に大きな影響を及ぼしました。高級食パンの品質を維持するためには、高価な材料が必要であり、それに加えて人件費の上昇は経営を圧迫しました。これにより、多くの店舗が採算に合わず、閉店を余儀なくされたのです。
これらの要因が絡み合い、高級食パンブームは急速に衰退しました。店舗の過剰展開は特筆すべき点で、珍しさを失ったと同時に、商品の持続的な魅力を失いました。経営環境の変化も、このブームの寿命を決定づけた要因と言えるでしょう。しかし、この経験は飲食業界にとって、今後の経営戦略を考える上での重要な教訓となるのは間違いありません。
4. 高級食パンから学ぶこと
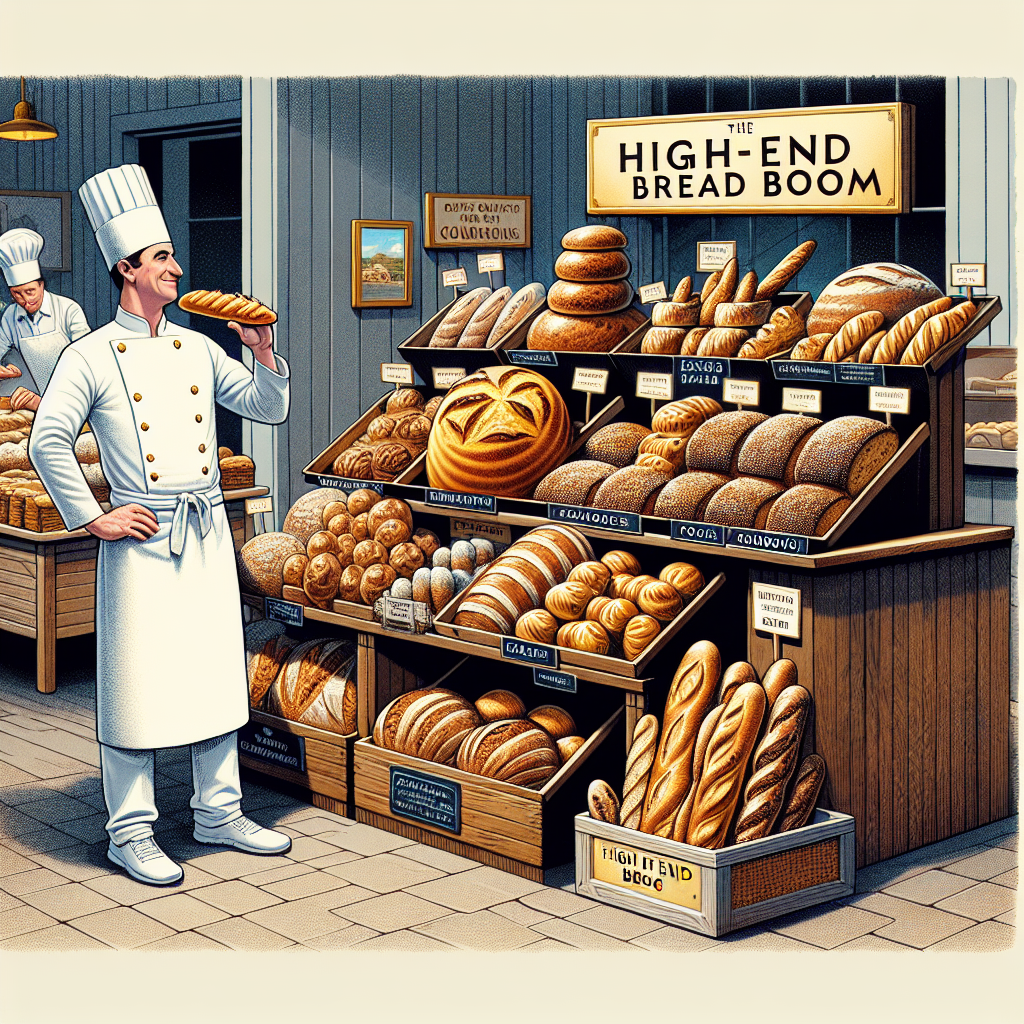
高級食パンは1本2斤で1000円近くと、市販の食パンの3〜4倍の価格にもかかわらず、プチ贅沢として多くの人々に支持され、多くの専門店が賑わいを見せました。
しかし、一時のブームが終わると、多くの店舗が閉店し、消えていきました。
このブームの背景には、商品の魅力だけでなくメディアの影響も大きく、メディアが消費者の関心を掻き立て、多くの消費者を店舗へと足を運ばせました。
特に『乃が美』や『銀座に志かわ』などのブランドがメディアに取り上げられ、この波に乗って他の多くのブランドも店舗を拡大しました。
しかし、ブームは長く続きませんでした。
顧客が飽きたことや原材料費の高騰、競争の激化が経営を圧迫し、特に『銀座に志かわ』はピーク時の140店舗から50店舗前後にまで減少しました。
このように、一過性の流行はその名の通り一瞬で消え去る可能性を秘めているため、持続可能なビジネスモデルを築くことの重要性が浮かび上がります。
高級食パンブームが教えてくれるのは、流行に追随するだけでなく、持続的に消費者に価値を提供できる新たなビジネスモデルの開拓です。
さらに、飲食業界の今後を考える上で、高級食パンブームの経験は貴重な教訓となります。
大切なのは、一つの商品に依存しすぎることなく、多様な消費者ニーズに応えられる柔軟性を持つことです。
このような視点を持つことで、今後の新たなトレンドをリードし続けることができるでしょう。
まとめ

一部の食パンは1本2斤で1000円近くするなど、通常の市販品と比べると非常に高価でしたが、消費者にとっては日常に少しの贅沢を取り入れるための手頃な手段として支持されました。
このブームがピークを迎えた時には、全国に1000以上の高級食パン専門店が出店され、その盛り上がりを見せました。
メディアの影響も強く、数多くの特集や見出しによって、消費者の購買意欲が刺激され、多くの人が店舗に足を運びました。
特に、『乃が美』や『銀座に志かわ』などの特定のブランドは、大きな注目を集め、その人気に乗じて急速に店舗を展開していきました。
しかし、ブームの終焉は早く、飽きた消費者や競争の激化に直面した多くの店舗は閉鎖を余儀なくされました。
興味深いのは、高級食パンブームの始まりは『乃が美』にまで遡ることができ、その特徴的な“生食パン”が中心的な人気を博しました。
生クリームや蜂蜜を使用したそのしっとりとした食感は、トーストせずそのまま楽しむ新たな食べ方を消費者に提案しました。
また、セブン-イレブンもこの流れに乗り、高級路線の『セブンゴールド 金の食パン』を発売し、大ヒット商品となりました。
しかし、ブームが急速に廃れていった理由として、多すぎる店舗の乱立による希少価値の低下や、商品の価値が消費者にとって続かなかったことが挙げられます。
これは、高級食パンが他の商品に転用しづらい特性を持っていたこと、そして原材料や人件費の高騰が影響したとも言えます。
こうしたブームの終わりを迎えた今、これらの一時的な現象から私たちは多くを学ぶことができます。
それは、飲食業界における新しいトレンドをつくるための良い教訓となり得るでしょう。