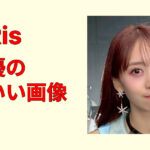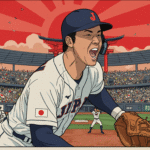|
“配達員によるオートロック解錠”宅配増で政府検討も「便利だけどちょっと怖い」賛否の声 国交相「防犯やセキュリティー大前提」 …ネット通販の普及などにより宅配便が増え続ける一方で、物流業界の人手不足は深刻化しており、政府は「配達員によるオートロックの解錠」を検討している。宅配… (出典:FNNプライムオンライン) |
1. 日本の宅配便の需要増加と人手不足問題

特に深刻なのは、人手不足の問題です。
宅配便の需要は急激に増加した一方で、配達員を確保することが難しく、多くの企業が遅延や業務の効率性に影響を受けています。
宅配の現場では、配達先での不在が多いため、再配達や持ち戻りが頻繁に発生しています。
この問題を改善するために、政府は「配達員によるオートロックの解錠」を2026年度には導入することを目指しています。
具体的な例として神奈川県内の宅配業者の調査では、配達先の7軒中4軒が不在の状態であり、効果的な配送が妨げられていることがわかります。
このような状況の背景には、オートロックシステムが存在しています。
配達員は集合住宅にアクセスしづらく、効率的な配送が困難になっています。
その一方で、セキュリティへの懸念から、住民の理解と協力が必要です。
国土交通省は、住民の安全を確保しつつ配送を効率化する方法として、オートロック解錠システムの導入を慎重に進めています。
2. 配達現場の実情:不在率とオートロックの壁

その一方で、物流業界は深刻な人手不足に直面し、配達の効率化が急務となっています。
その中で特に問題となっているのが、配達先での不在の多さと、それに伴う再配達や持ち戻りの頻発です。
最近の政府の動向として、配達員によるオートロックの解錠が検討され始め、2026年度の導入を目指しています。
しかしながら、現場では依然として多くの課題が残されています。
神奈川県内のある宅配業者への取材によると、特に集合住宅においては、配達先7軒中4軒が不在であり、置き配が可能だったのは1軒のみとの報告があります。
このような不在問題に直面する背景として、特に集合住宅ではオートロックが配達の大きな障壁とされています。
現場の配達員である吉田寅彦さんは、置き配が可能であれば配達の効率が向上し、配達員の体力的な負担の軽減に繋がると指摘しています。
しかし、オートロックを解除するシステムの導入には、セキュリティ面での課題も浮上しています。
また、街の住人の声としては、「不在時の荷物の受け取りが難しい」「誰でも入ってこれるのは不安」という意見もあり、セキュリティへの警戒感が強まっています。
過去に神戸市で起きた不法侵入事件もあり、配達の効率と住民の安心・安全をどう両立させるかが今後の課題と言えるでしょう。
対策として、一部のマンションでは、住民がスマートフォンを使って配達員と対話したり、映像で確認したりするシステムが導入され始めています。
これにより、配達員以外の不審者の侵入防止が図られています。
しかしながら、普及にはさらに時間がかかりそうです。
配送システムの効率化とセキュリティのバランスを取ることが、物流業界の未来にとって重要な戦略の一つとなるでしょう。
3. オートロック解錠システムの導入背景

この急増する需要に対して、物流業界は深刻な人手不足により、効率的な配送の必要性が高まっています。
その中で注目されているのが「オートロック解錠システム」の導入です。
特に集合住宅での配達において、不在による再配達や持ち戻りが頻繁に発生し、これが配送現場における大きな負担となっています。
政府は2026年度までにこの状況を改善すべく、配達員がオートロックを解錠できるシステムを導入したいと考えています。
現場の声にもその緊急性が表れており、神奈川県内の取材では、7件中4件の配達先が不在であったというデータが示されています。
しかし、これを改善するための鍵となる可能性があるのが置き配です。
配達員の吉田寅彦さんは「置き配が可能になれば、配送効率が大幅に向上する」と語っています。
この背景には、物流業界の労働力不足があり、加えて国土交通省はデータ共有を通じて安全性を高める手法を模索しています。
しかし、住民の間ではセキュリティに対する懸念も根強く存在しています。
不在時の荷物の受け取りが容易になる点は歓迎されますが、同時に「誰でも勝手に入って来られるのではないか」という不安も拭い去れません。
4. セキュリティと住民の合意形成

その要となるのがセキュリティ対策です。
住民の安全を確保しつつ、物流効率を向上させるためには、両者のバランスを保つことが求められています。
スマートフォンを活用した新しい住民確認システムの試行が始まっています。
このシステムでは、配達員がオートロックを解錠する際、スマートフォンを通じて住民自身が配達員を映像や通話で確認できるようにします。
これにより、不審者の侵入を防ぎながらも、効率的な荷物の受け取りが可能になります。
特に注目すべきは、神戸市で発生した不法侵入事件です。
この事件は、全国的に大きな衝撃を与え、セキュリティ意識を高める契機となりました。
このような事件を防ぐためにも、住民の意識改革が不可欠です。
中野国交相も、オートロック解錠システムの導入には住民の合意を必要とし、防犯対策を大前提とする姿勢を明らかにしています。
新しいシステムの導入に向けては、住民の安全を第一に考え、合意形成を時間をかけて進めることが重要です。
5. 配送効率とサービス改善の提案

ネット通販の急速な拡大に伴い、物流の需要が増える一方で、配送過程での課題も明確化しています。
特に不在配達の頻度が高まっており、再配達による効率の低下が深刻です。
物流の効率化を考えると、政府が積極的に導入を検討している「オートロック解錠システム」は重要な戦略と言えるでしょう。
この解錠システムの導入により、配達員が効率良く働ける環境が整うことで、人手不足の問題にも対策が打てます。
しかし、システム導入には住民の同意が必要で、セキュリティ対策が最大の課題です。
特に、不法侵入のリスクを軽減する工夫として、住民がスマートフォンを通じて配達員を確認できる仕組みの導入が進められています。
また、配送効率の向上を目指すための提案として、政府による宅配ボックスや置き配に対する補助金制度が考えられています。
この制度は、配達先の不在時にも荷物の受け取りを可能にし、再配達の頻度を下げるのに役立ちます。
さらに、再配達に料金を課すといった制度の導入も提案されており、これは受け取り意識を高め、結果的に配送現場で働く人々の稼働効率を引き上げる一助となるでしょう。
一方で、日本の物流業界はサービスの過剰さが批判されることがあり、顧客の期待値を適切に見直すことが求められています。
再配達を減らす取り組みは、サービスの効率化だけでなく、従業員の負担軽減にも大きく寄与します。
物流業界の持続的な発展を目指し、サービスの提供方法を再検討し、顧客と業界全体の意識改革を進めることが急務です。
日本が誇る質の高いサービスは維持しつつも、持続可能な形で現代のニーズに対応していくことが求められています。