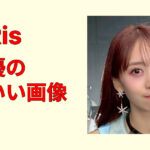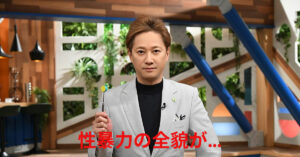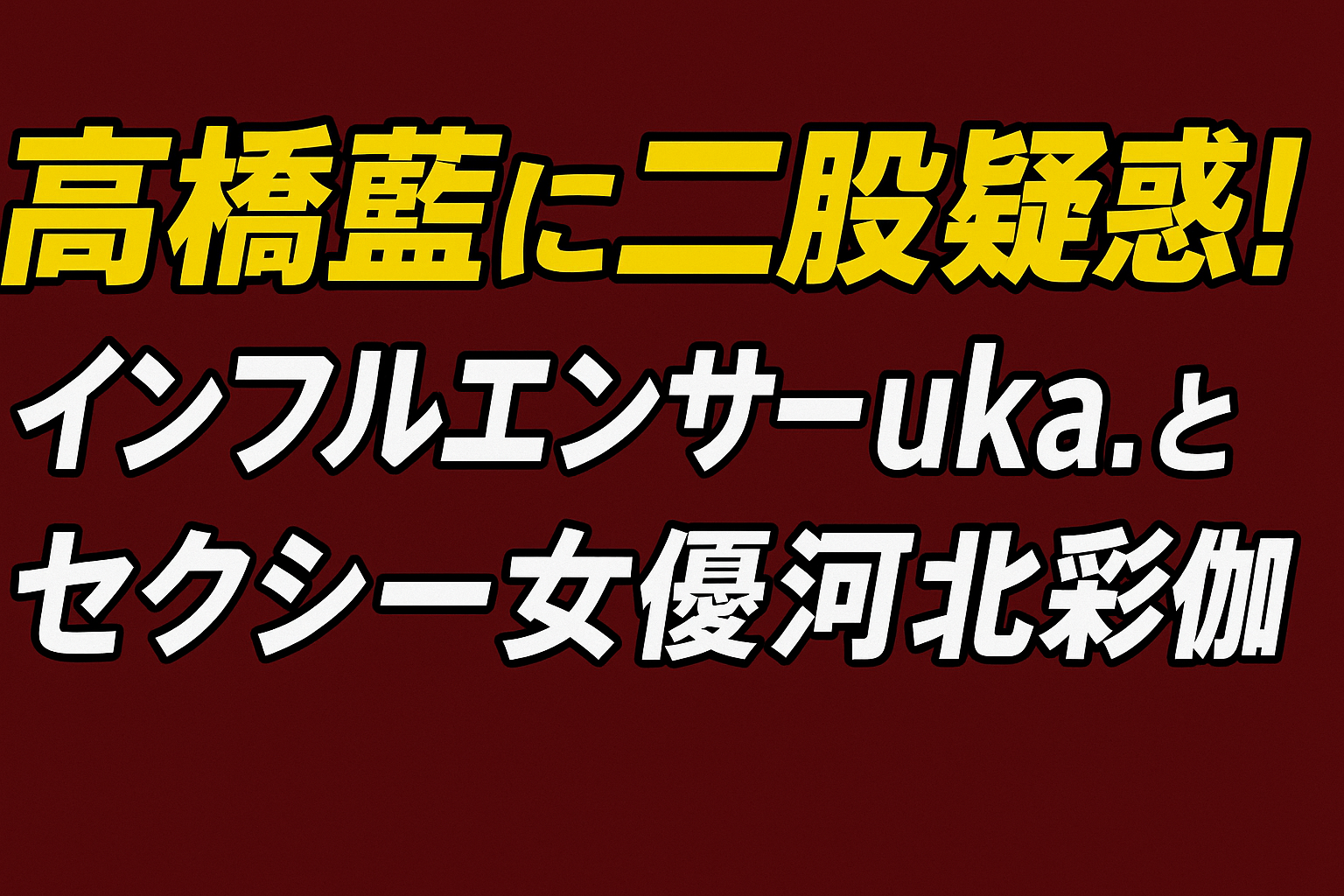|
準絶滅危惧種の海鳥、野生化したネコが年3万羽以上捕食か…世界最大の繁殖地・御蔵島で 国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されている海鳥「オオミズナギドリ」が、伊豆諸島・御蔵島(東京都御蔵島村)で野生化した… (出典:読売新聞オンライン) |
1. オオミズナギドリの危機と御蔵島の現状
|
オオミズナギドリ(大水薙鳥、Calonectris leucomelas)は、ミズナギドリ目ミズナギドリ科オオミズナギドリ属に分類される鳥類。日本のミズナギドリ科のなかでは最大種で、日本では春から秋にかけて最も普通にみられるミズナギドリ類であり、よく陸からも観察される。…
14キロバイト (2,026 語) - 2025年8月4日 (月) 03:36
|
1970年代の後半には、御蔵島内でのオオミズナギドリの推定個体数は175万羽を超えていましたが、最新の調査ではわずか約10万羽にまで減少していることが確認されています。この現象は、急激な人口減少の明示的な例であり、島全体が国立公園に指定されているにも関わらず、自然保護の取り組みが未だ不十分であることを示しています。また、ノネコの待ち伏せと捕食行動は、これまで考えられていたよりもさらに早い段階、つまり1月から開始されていることが新たに判明しました。
この問題に対処するには、ノネコの効果的な管理と捕獲、そして保護体制の強化が不可欠です。森林総合研究所の亘悠哉チーム長は、人手と機材の充実が急務であるとし、さらなる調査と対応が必要であると訴えています。世界的な視点から見ても、猫と生態系への影響は非常に大きく、米国やオーストラリアでの実態は、その深刻さを物語っています。猫はまた、人獣共通感染症の媒介としても知られており、その影響は人間社会にまで及んでいます。
私たちが直面しているのは、動植物が共存する環境の持続可能性に関わる深刻な課題です。このような状況を改善するためには、問題の根本に立ち返り、具体的な対策を講じる必要があります。
2. ノネコによる捕食問題の実態

森林総合研究所を中心とした研究チームは、昨年行ったフンの調査に基づき、1匹のノネコが年間約330羽のオオミズナギドリを捕食していると推定。この調査結果に基づき、2022年度には御蔵島村で106匹のノネコが捕獲されました。このことから、推計される捕食数は年間3万4980羽に及ぶとされています。
オオミズナギドリは世界的にも非常に重要な繁殖地である御蔵島で、過去数十年でその数を大幅に減少させており、1970年代の推定175万羽以上から2016年には約10万羽まで減少しました。このような減少を受け、2018年にはIUCNがこの鳥を準絶滅危惧種に指定しています。このような危機的状況の中、ノネコによる捕食は深刻な問題とされています。
さらに、新たな調査によれば、オオミズナギドリはこれまで考えられていたよりも早い1月には御蔵島に帰島し始めており、捕食被害はこれまでの評価よりも大きい可能性が見えてきました。このため、ノネコの捕獲および保護活動の強化が急務とされています。森林総合研究所の亘悠哉チーム長は、そのためにはさらなる資源の投入が必要であると指摘しています。
ノネコによる捕食問題は、御蔵島だけでなく、世界的にも広がる猫の生態系への影響を映し出します。適切な管理と対策を講じることが、オオミズナギドリの保護には欠かせません。
3. 捕食被害の評価と保護の必要性

オオミズナギドリは、国際自然保護連合(IUCN)によって準絶滅危惧種に指定されている海鳥であり、その保護が急務とされています。
御蔵島を繁殖地とするこの鳥は、ノネコによって年間で3万羽以上も捕食されている可能性があると報告されています。
これにより、オオミズナギドリの個体数は大幅に減少し続けています。
さらに、2018年に行われた調査に基づき、これらの評価が見直される必要があります。
近年行われた調査では、オオミズナギドリの繁殖時期における島への帰島が従来考えられていた3月からではなく、1月から始まっていることが判明しました。
この新しい情報により、これまでの被害評価は見直しが必要とされ、その実行が求められています。
ノネコの捕食が繁殖期に重大な影響を与えているため、捕獲および保護の正確な方法の確立が重要です。
オオミズナギドリの減少を防ぐためには、ノネコの捕獲と保護活動の強化が必要です。
地域の保護団体や自治体、そして研究機関が協力し、ノネコの管理とオオミズナギドリの保護を進めることが欠かせません。
適切な捕獲方法の導入や、人手および機材の充実により、より効果的な保護活動が可能となるでしょう。
オオミズナギドリだけでなく、他の島の生物多様性保護にもつながる取り組みが、私たちの環境や共存に対する考え方を再評価する機会を提供してくれます。
持続可能な自然環境の保全に向けて、多くの人々が一丸となって努力することが求められています。
4. 生態系への猫の影響

例えば、国際自然保護連合(IUCN)によって準絶滅危惧種に指定されているオオミズナギドリは、伊豆諸島・御蔵島において野良猫による捕食に直面しています。この島はオオミズナギドリの世界最大の繁殖地でありながら、1年間で約3万羽がノネコに捕食される可能性があるとされています。オオミズナギドリの個体数はここ数十年で大幅に減少し、この地域では深刻な環境問題となっています。
また、猫の影響は鳥類だけに留まりません。米国においては年間10億羽の鳥類が猫によって命を落としているとされ、オーストラリアでも猫が1日で100万羽以上の鳥類を捕食するという報告があります。さらに、猫は人獣共通感染症をもたらすリスクもあり、健康被害の原因ともなり得ます。
このような状況を改善するためには、飼い猫の室内飼いを徹底することが考えられます。室内飼いを実践することで、猫自身の安全性を確保するだけでなく、地域の生態系を守る手助けともなるのです。飼い主には猫を自然環境に出さない義務があり、これにより生態系へ与える負の影響を抑制することが必要です。
5. 問題解決のための意識と行動
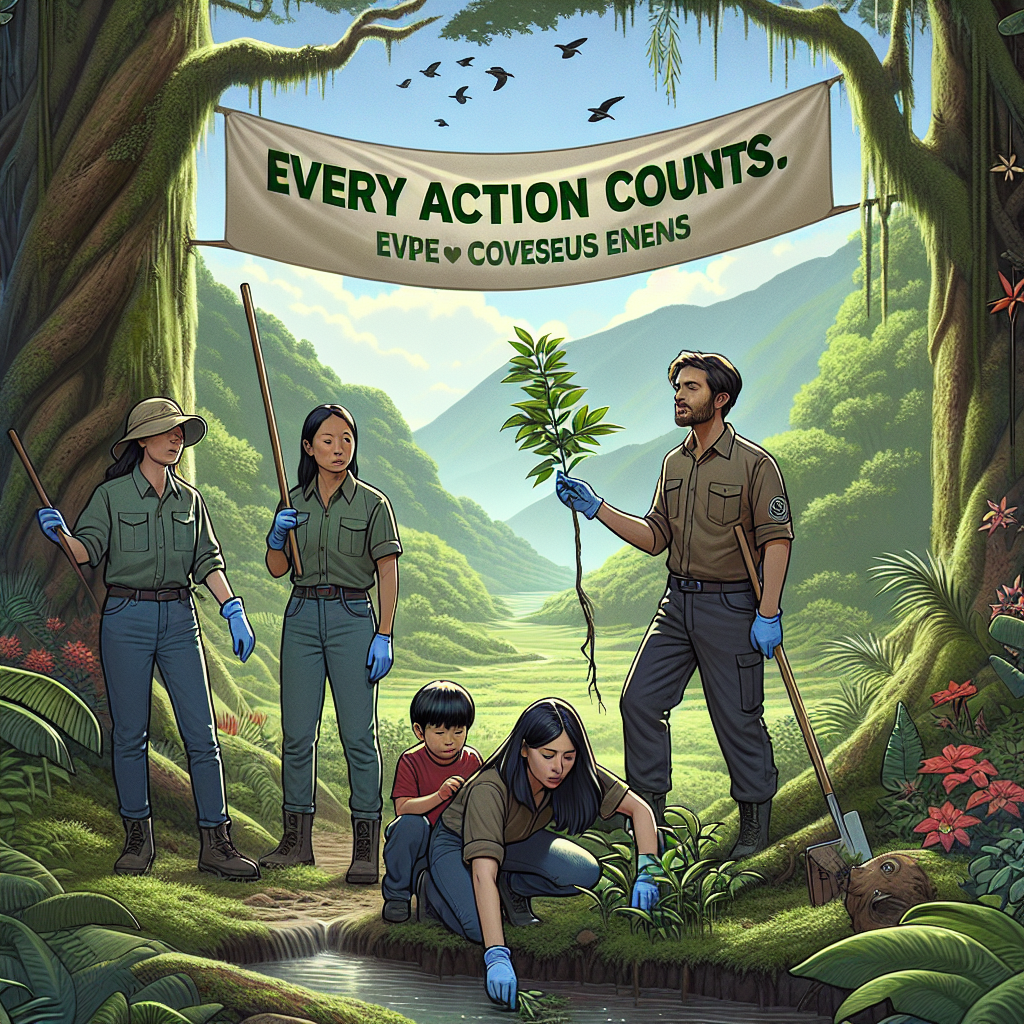
野生化した猫、いわゆるノネコが御蔵島で毎年数万羽ものオオミズナギドリを捕食している現状が、森林総合研究所によって公表されました。
ノネコ問題は単なる個別の問題にとどまらず、世界中で生態系の保護と動物の安全に関わる重大な問題となっています。
オオミズナギドリは御蔵島を世界最大の繁殖地としていますが、その数は急速に減少しています。
1970年代後半には175万羽以上いたとされていますが、現在では10万羽を切ると言われており、このままでは絶滅の危機にさらされる可能性があります。
このような状況を改善するためには、ノネコの捕獲と保護が必要であり、それには地域社会全体の協力が不可欠です。
特にペットの猫については、完全室内飼育を推奨することで、生態系の保護と飼い主自身の責任が問われます。
これにより、猫自身の安全はもちろん、人獣共通感染症のリスクも低減されるでしょう。
最終的には、飼い主に対する適切な飼育指導の提供が重要であると考えられます。
自然保護の取り組みは、個人の意識と行動が大いに影響します。
環境問題は一人の努力では解決しませんが、個々が持続的に取り組むことで変化を起こすことができます。
社会全体の意識改革を図り、より良い未来を築くために、私たち一人ひとりが行動することが求められています。