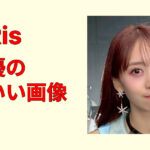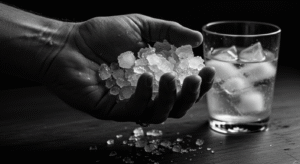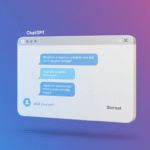|
紙の保険証“有効期限切れ” マイナ切り替えで戸惑い 資格確認書で受診も …有効期限切れになり、病院の窓口では朝から対応に追われています。 マイナ切り替えで戸惑い70代 「いつもは保険証でしてました。きょうはマイナンバーカードで」… (出典:テレビ朝日系(ANN)) |
1. マイナ保険証移行の概要

2023年10月1日から、医療の現場ではマイナ保険証への移行が本格化しています。この新制度導入に伴い、多くの医療機関、特に高齢者が多く訪れる病院ではその対応に追われている現状があります。患者も医療スタッフも、初めて利用するマイナ保険証に戸惑う場面が多々見られています。
具体的には、後期高齢者医療制度や国民健康保険の加入者にとって、7月末での従来の健康保険証の有効期限切れを機に新たなシステムに移行しなければなりません。この移行は多くの病院で課題を引き起こしています。医療現場では、マイナ保険証の利用方法を高齢者に説明する必要がしばしば生じており、紙の保険証を未だ持参する患者への対応も求められています。
厚生労働省は、2024年3月末までは紙の保険証でも病院側が確認することで受診が可能であるとしつつ、マイナ保険証を持たない患者への支援策として「資格確認書」を送付しています。これにより、紙の保険証を持参した人でも引き続き医療を受けることが可能になります。しかし、この新たな試みには、従来の制度と比較して多額のコストがかかることが避けられないと指摘されています。
この背景には、国の「データヘルス改革」として医療と介護のデジタル化(DX)を進める広範な施策があります。マイナ保険証の普及により、患者個々の医療や介護のプランがより最適化され、効率的な運用が期待されています。とはいえ、この導入には混乱が伴い、反発も少なくありません。従来の「給付と負担」の原則を崩さずに、無駄を省くための新たな方策が求められています。
将来的には、マイナ保険証の広がりが行政コストの削減へと繋がることが期待されています。しかし、既存の制度と新制度の比較において、有効性が納得される形で展開されることが重要です。そのため、利用者への情報提供の徹底と必要な支援が不可欠です。
2. 現場での対応と課題

特に高齢者の多い医療施設では、窓口での対応が急務となっています。多くの高齢患者が初めてマイナ保険証を使用する際に混乱を生じており、そのための支援が欠かせません。
医療スタッフは、従来の健康保険証からの移行をスムーズに進めるための説明をしなければならない場面が多々あります。
また、有効期限の切れた紙の保険証を持参する患者への対応も重要な課題です。
これに対処するため、厚生労働省は「資格確認書」を送付し、紙の保険証を持つ患者が医療を受け続けられるよう配慮を行っています。
さらに、現場では患者自身が制度の変更を全て理解していないことが多く、その結果スタッフの説明が必要となります。
この変化にはコストと手間がかかるが、それ以上にデジタル化の恩恵を患者に届けるためには、丁寧で理解しやすい説明が必要です。
現場での課題を改善するためにも、利用者への周知徹底と継続的な支援が求められています。
3. マイナ保険証のメリットとデメリット
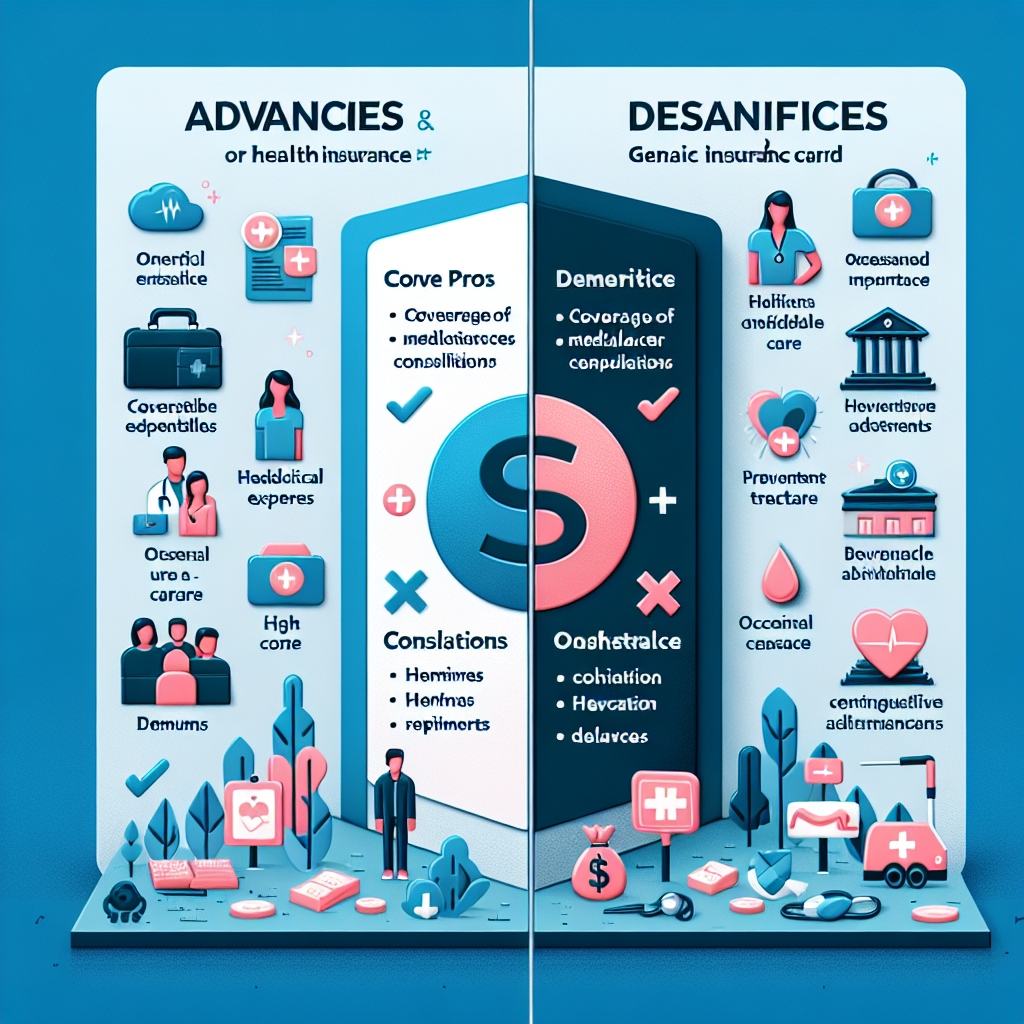
マイナ保険証の導入が進む中、そのメリットとデメリットが多くの人々の関心を集めています。まず、メリットとして挙げられるのは、医療と介護の分野でデジタル化が進むことにより、患者一人ひとりに合わせた医療サービスが提供される可能性が高まるという点です。これにより、医療の質が向上し、効率的な医療システムが構築されることが期待されています。
一方で、導入に際してはいくつかの課題が存在します。まず、高齢者を中心に新しいシステムへの移行に対する混乱が見られます。多くの高齢者は、従来の紙の保険証に慣れており、新たなデジタル保険証の使い方に戸惑うケースが後を絶ちません。また、技術やデジタル機器に不慣れな方々にとって、マイナ保険証を用いることへの抵抗感が一因となることがあります。
さらに、システム導入には多額のコストがかかりましたが、その負担を国民がどのように受け止めるかも重要なポイントです。費用対効果を考慮しつつ、どのように行政コストを削減しつつ、サービスの質を保つかが問われています。技術革新だけでなく、制度の運用面でもしっかりとしたサポート体制が求められています。
このように、マイナ保険証の普及にはさまざまな側面がありますが、最も重要なのは利用者への十分な説明と支援体制の整備です。国民一人ひとりが安心して新しい制度を利用できるよう、適切な情報提供と支援を行うことが不可欠です。マイナ保険証が国民のためのより良い医療サービスの提供に繋がるよう、これからも準備を進めていくことが望まれます。
4. 利用者支援の必要性

マイナ保険証の導入という新しいステージにおいて、利用者への支援が不可欠です。特に高齢者に対する支援が重要視されています。都内の病院では、マイナ保険証への移行に戸惑う高齢者の姿が日常茶飯事となっています。その理由の一つに、新しいシステムを理解するための情報が十分に提供されていないことが挙げられます。情報が不足しているため、窓口での説明が必要となり、医療スタッフの負担が増加しています。このような状況では、利用者が安心して新たなシステムを利用できるよう、分かりやすい情報の提供と、初歩的な段階での手厚いサポートが求められます。
このような対応策の一つとして、厚生労働省は「資格確認書」の送付を行っています。この書類は、マイナ保険証を持たない人々が健康診療を引き続き受けられるよう配慮されたもので、保険証のような感覚で使用することができます。ただし、この「資格確認書」自体も、新しい形態であるため、多くの高齢者がその使い方に戸惑う可能性があります。したがって、この書類の使用方法についても、しっかりと説明を行う必要があります。
また、地域に密着した情報セッションや、医療機関でのウェルカムデスク、あるいは専任のスタッフを配備するなど、高齢者が容易に情報を得られる環境作りが急務です。これにより、マイナ保険証への移行がスムーズに行われると同時に、利用者の不安を和らげることが可能となります。
行政側としても、デジタル機器に不慣れな高齢者や特別な支援を必要とする人々に対して可能な限りのサポート体制を整え、利用者一人ひとりが納得した形で移行できるよう努めることが求められています。これらの取り組みは、最終的に無駄の削減や効率化、そして行政コストの削減にも寄与する可能性があります。
まとめ

この施策が成功するには、利用者である患者の理解と協力が不可欠となります。そして、サービスを提供する医療機関側にも、新しいシステムに対する柔軟な対応とサポートが求められます。
特に高齢者が多い病院では、彼らが戸惑わないよう、使い方の説明やサポートが重要です。
東京都内の総合病院では初日から戸惑いが見られ、多くの患者がマイナンバーカードを持ち込んだものの、使い方に四苦八苦していました。
後期高齢者医療制度の加入者などは、従来の保険証が使えなくなるため、7月末までにマイナ保険証に切り替えが必要となっています。
これに伴い、厚生労働省は「資格確認書」を配布し、マイナ保険証を持たない人々への配慮も進めていますが、まだまだ現場では混乱が見られます。
この新しいシステムは医療の効率化に寄与することが期待されていますが、大多数の患者が変更事項を知らずに受診しに来る現状では、病院職員の説明や支援が欠かせません。
さらに、医療と介護のデジタル化を促進する背景には、行政コストの削減を図る「データヘルス改革」と呼ばれる広範な施策があります。
これにより、患者に最適化された医療・介護サービスの提供が見込まれていますが、従来の保険制度の「給付と負担」の原則が揺らぐリスクもあります。
技術革新を推し進める際には、利用者への周知徹底と適切な支援が非常に重要です。
その一環として、無駄のない方策で現行制度を補うことが注目されています。
マイナ保険証の普及は、将来的に行政コストを削減する可能性も含んでおり、そのためには納得のいく形での進行が鍵となります。
共に歩み、新しいシステムを支えていくことが、みんなにとっての利益となるでしょう。